Members Column メンバーズコラム
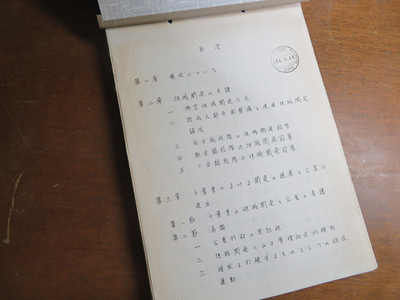
最近気になった言葉から
杉浦美紀彦 (ひょうご産業活性化センター) Vol.733
「お金を払って参加するのは自分より若い人達の集まりに行くとき」*1
これを耳にして、お金を払う払わないは別として、当然、私も自分より若い人と交わるよう努力しなければならないと思いました。心がけようと思っている程度なのですが、サイエンスフェアin兵庫に参加する理由にそうした気持ちも含まれます。
「難しい本を読むときには、電車に持ち込んだりします。」
どこかで本*2を立ち読みした際に残った言葉で、うろ覚えの正確な言葉ではありません。じつは今思い出しただけで最近目にした言葉でもありません。ただ、大江健三郎の言になるというところにポイントがあります。あの大江健三郎も難解な本の前ではひるむことがあるのだと、そして、それにきちんと対処しているのだということを知って、二重の意味で印象に残っています。
「僕は、センスという言葉を、『知識とパターン認識』だと考えているんですね。」*3
目にした時、「えっ」と思いました。センスを分解なり分析なりするという視点は全く持ち合わせていませんでした。つまりは、センスという言葉で満足して、思考停止させてきたわけですね。別の方(音楽家)の「何か音楽を聴くとしますわね。で好きになる。ファンとして模倣したりする。その了見の程度で何かやってると所詮はエピゴーネンなわけ」*4という指摘にうなずきながら、自分がその了見に留まっていることに気付かされました。思えば、学生時代から、例えば卒論を書く段になって、ほわほわした問題意識はあるのだけれど、課題が設定できないなあとは感じていましたが、それはまさに「ある世界を凝視して、そこに新たな精神の器の顕現を聴きだすところまで透徹しているか?そういう問いかけ」をしてこなかっただけという事実を突きつけられ、少し頑張らなきゃと思っています。
その頑張る方向性については、「『知識』から『パターン』が生まれてくる部分があります」と示していてくれています。そうして得られるパターン認識は「暗黙知」とも言い換えられるのですが、それを身に付ける前提として「測定できないことは改善できない」というところに立ち戻ります。パターンを見出す「『嗅覚』は、どうしたら鍛えられるのかといった話もあるのですが、まずは対象を観察・分析するところから始めなければならないようです。そう考えると、この方が言語化することや、メモをすること(きちんと後で読み返せるように奇麗に)の重要性を説くこともよくわかります。
「ある程度の時間をかけて計画的に行わないと変化に対応出来ない人が仕事からあぶれ、変化に対応出来ない会社が無くなって行く未来が見えます。」*5
ある中小企業の経営者の言葉です。変化に対応出来ない会社が無くなって行くといった言葉はよく目にしますが、実際に当事者として立ち向かう立場となったらどうか。私の想像を超える苦労に言葉はありません。同時に、変化に対応出来ない人にまで気持ちが及んでいることに着目したいです。この経営者の言葉は、自分の会社経営の枠を越え、「変化に強い人を育てる時間が必要だと思います」と続きます。
いろいろなところで人手不足が叫ばれ、それが常態化して久しい気がします。嫁の実家が尼崎の中小企業だったりするので、私も実際に見聞きしたことがあります。一方で、先日、私の所属部署で週4日勤務の嘱託を募集したところ、20人の応募がありました。単なるミスマッチの問題でしょうが、採用される一名を除く残りの方々を考えると、再就職をあきらめる方がいらっしゃるのではないかと想像した時に目に止まったのが、日本の労働市場は全体として超過供給状態にあるにもかかわらず、失業率が上がらなかったのは、失業から非労働者化してしまったことによるという指摘*6です。ハローワークを通じた求職活動をしなくなった人達が増えたということですが、人手不足の状況から零れ落ちて、待遇の低い求人であっても応じる人達が既に増えているということにもなるのでしょう。
こうした状況で無理やり賃上げしても、悪いことにしかならないように思えてしまいます。そもそも「本来、賃上げは、生産性の向上によって実現すべきものだ」という指摘*7の方がしっくりきていますので、やはり、企業として生産性の向上を図りつつも、変化に強い人を育てる時間が必要というところに立ち返る気がします。
*1:新井秀美さんの言葉。2024年12月6日(金)に開催されたKNSオープン・サイエンス研究会で話題提供いただいた際の発言からです。
*2:大江健三郎「『自分の木』の下で」(朝日新聞出版 2001年6月15日発行)という本です。
*3:楠浦崇央さんの言葉。彼が代表取締役社長を務めるTechnoProducer 株式会社が発行するメルマガ「e発明塾通信 vol.1149」(2024年12月2日号)より。
*4:伊東乾さんの言葉。2024年12月21日に彼が発信したXより
*5:井上佳宣(㈱井上模型製作所)さんの言葉。はい。前回(2025年2月5日発行)のKNSメンバーズコラムVol.732からですね。
*6:斎藤誠「なぜ、実質賃金が低下しているのか?:新型コロナ禍後の内外の経済環境を踏まえて」(2024年12月24日 RIETI [BBLセミナー])
*7:野口悠紀雄「日本を破綻に導く「英国病」の再来か?平均賃上げ率5%超えも手放しで喜べないワケ」(2024.11.7 ダイヤモンド・オンライン)
※写真は、棚の奥から引っ張り出してきた卒論です。表題が貼ってあったはずなのですが、見当たらないので、目次部分を写しました。

