Members Column メンバーズコラム
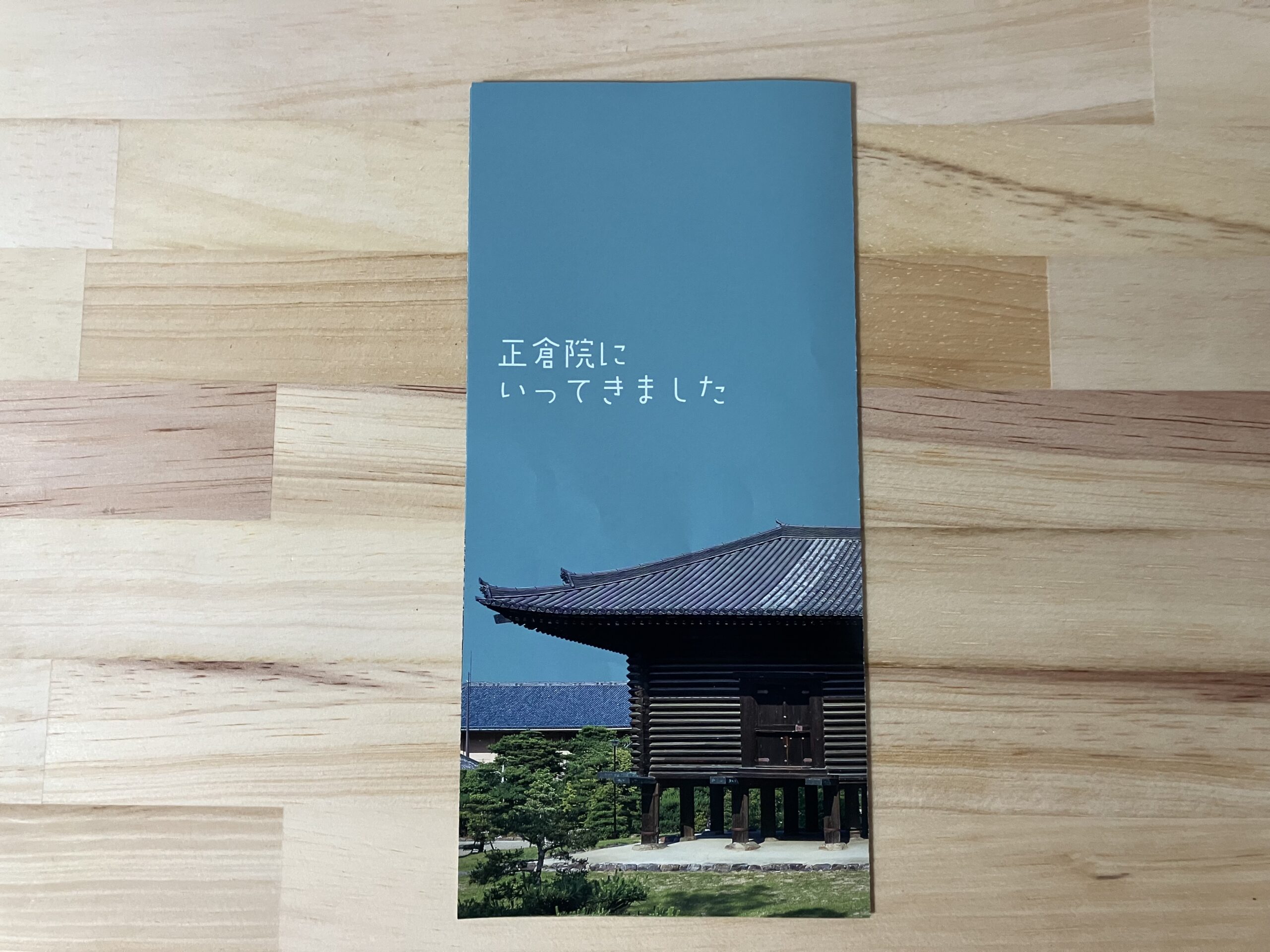
「正倉院展」の時期に思うこと
小川睦 Vol.771
暑すぎる夏がようやく終わりをみせ急に朝晩が寒くなってきました奈良よりお送りいたします。気が付けばいつの間にやら11月ですね。時事ネタを、と思いましたので、奈良の秋のイベントにまつわるお話にしようかなと思います。
ご存知のかた、行ったことがあるよというかたが多いことを祈って、「正倉院展」のお話をします。
奈良国立博物館で毎年秋に開催される「正倉院展」は、奈良・東大寺の正倉院に伝わる約9,000件の宝物の中から厳選された品々を一般公開する特別展です。今年の開催で第77回を迎えました。毎年、10月末〜11月初旬にかけて開催されています。聖武天皇ゆかりの遺愛品や奈良時代の朝廷・貴族・寺院で使用された工芸品、文書、楽器、調度品、仏具などの展示で構成され、東西文化の交流を象徴する国宝級の文化遺産を拝見することができます。
今年の展示では、正倉院宝物の中から計67件が公開されます(そのうち6件が初出陳だそうです)。今年のポスターのメインビジュアルになっている青いガラスの器「瑠璃坏(るりのつき)」は、当時の精緻な技術と美意識が象徴されている宝物です。現代の感覚でも分かりやすく美しいな、デザインが面白いな、と感じます。
「正倉院はシルクロードの終着点である」と言われます。様々な国や地域の宝物が巡り巡って正倉に辿り着き保存管理されているので、日本の奈良時代の文化を示すだけでなく、8世紀の世界の文化を代表する貴重な文化財が多く残っているからです。聖武天皇と光明皇后にゆかりのある調度品をはじめ、東西文化が交わる奈良時代の国際的な美意識を伝える工芸・装飾・宗教具など多様なジャンルの宝物を一挙に見られるのが正倉院展の魅力と言えます。
正倉院展は、1889年の奈良国立博物館開館以来、戦後の中断を経て毎年秋に開催されていて、奈良時代の文化を現代に伝える日本屈指の古美術展として定着しています。毎年、保存環境を考慮して異なる宝物が展示されるため同じ品を何度も見ることはほとんどなく、毎年新たな発見があることも魅力の一つです(と言いながらも人気の宝物(いわゆる分かりやすく綺麗・面白い・華やかな宝物)は数年周期で見られる印象です)。
そもそも正倉院宝物の起こりは、崩御された聖武天皇のご冥福を祈るため、光明皇后が遺愛品を東大寺の大仏様に献納され、これらを正倉に収めたことから始まります。正倉とは、奈良時代や平安時代の官庁や大きなお寺にあった倉庫のことです。このような正倉が集まった区画のことを「正倉院」と呼んでいました。現在の東大寺には一棟だけが残り、奈良時代から変わらず境内の同じ場所に佇んでいます。歴史的には東大寺の倉ですが、現在は宮内庁が正倉及び正倉院宝物を管理・保存しています。
この正倉ですが、校倉造りの高床式倉庫です。三倉に仕切られていて、北(正面向かって右)から順に北倉、中倉、南倉と呼ばれています。北倉と南倉が檜の三角材を井桁に組み上げた校倉造りです。校倉造りの代表的な建築物としても知られています(中倉は、北倉と南倉の壁を利用して南北の壁、東西両面は厚い板をはめて壁とした板倉造り)。高床式がどのくらい高いかというと、地面から床下まで約2.7mあります。現代人でもすっぽり余裕で収まるのですから、当時の人たちにとってはより高く感じられたのではと思います。落雷で焼損したり戦火にも見舞われましたが、奈良時代から変わらない場所に今も建っています(ちなみに、正倉そのものも国宝です)。間口33m、奥行9.4m、全高14mと古代に建てられた倉庫としては破格の大きさです。それだけ、奈良時代から東大寺が大きなお寺であったことがうかがえますし、天皇の宝物を入れておくにもふさわしい建屋だったことが伝わります。内部は2階建てになっています。
とはいえ、現在では宝物の安置は空調設備の整った鉄筋コンクリート造りの宝庫に移されているようです。正倉に代わって宝物の収蔵をしている宝庫も勅封です。奈良時代以来、宝物は勅封制度によって厳密に管理されてきました。勅封制度とは、天皇陛下の許可を無くして扉を開けられない、ということです。天皇陛下のご親書による封で現在も守られています。毎年秋に東京から勅使がお見えになり、勅封の扉を開きます。そして宮内庁の職員の方々が全ての宝物の点検をされます。この時に合わせて「正倉院展」が開催されるのです。虫干しのタイミングで見せてもらっているんだなぁと勝手に思っています。
ざっくりとした正倉院展(&正倉)のご案内でしたが、毎年思うことがあります。それは、「これだけの長い期間、それらを伝え、管理し、時には修理をしながら、守ってきた人たちがいる」ということです。正倉院展だけではなく、例えば他の寺社の祭祀ごとや地域のお祭り、風習、ことば、色んなことが連綿と地続きで続いているのは、それらを伝えてきた人たちがいてこそです。私はずっと奈良の人間なので、奈良のことしか知りませんが、みんなが大事に思っているからこそ続いているものが、奈良には多いなと思います。おそらくみなさんの地域でも同様だと思います。正倉院宝物は規模が大きすぎるので国単位のお話ですが、地域で大事にされてきたものの意味を考えつつ、時には姿を変えることもあるでしょうが、守り伝えていきたいなと。金木犀が香るこの時期に、いつも再確認するのでした。
参考:正倉院展公式HP( https://shosoin-ten.jp/ )、宮内庁正倉院HP( https://shosoin.kunaicho.go.jp/ )

